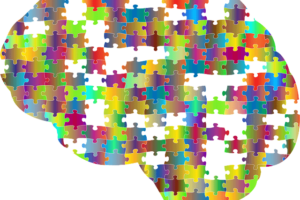目次
FBI,諜報員などのプロが使う嘘つきを見抜く方法
あなたは嘘をついたことはありますか?
少なからずあると思います。もし嘘をついた経験がないのであれば、ぜひともその正直さを見に付けたいので弟子入りさせてください笑
嘘をついている時はなんとも言えない不安感に襲われ、挙動不審になりがちですよね。
時折人と話しているときにも、”ウソっぽいな”と感じてしまうこともありますよね。なんだか嘘くさい。説明はできないかれども、嘘をついていると感じることが時折あります。
今回は、R. Edward Geiselman教授らが行った欺瞞に関する60件の研究のレビューの結果より嘘つきの見抜き方について紹介していきたいと思います。
なおガイゼルマン教授はFBI、海兵隊員、警察官、諜報員などに対してインタビュー技術等を教えているほどの人なので、信憑性のある嘘つきの見抜き方だといっていいでしょう。
特徴①嘘つきは質問を必要以上に繰り返す

難しい質問をされた際に、嘘つきは質問を繰り返したり、聞き返したりします。
嘘をついているため、質問に対する回答を考える時間が必要なんですねー。
「昨日は何してたの?」って聞かれた際には、「昨日は何してたの?って、家でゆっくりしてたよ」みたいな感じに質問を繰り返しながら回答したり、
「昨日は何してたの?」に対して、「え?なに?」というようにとぼけたりします。
「昨日は何してたの?」レベルであれば、さくっと時間差無く回答できるかもしれませんが、入り組んだ難しい質問をすると決まって時間稼ぎのために繰り返したり聞き返したりします。
いつもスラスラ質問に答えている人が、質問を繰り返したり、聞き直したりする回数が増えている場合は嘘をついている可能性が高いです。
特徴②嘘つきは話すスピードが変化する
嘘つきは話す速度が頻繁に変わります。
基本的に嘘をついている際に、嘘がバレそうな箇所や自信がない箇所については、早口になったりします。
早口でまくし立てて、都合の悪い部分から早々目を逸らさせようとするんですね。
その一方、嘘がバレることのない部分や真実の部分に関しては、早口ではなくある程度ゆったりしたスピードで話すことが多いです。
嘘がバレるかも・・と焦って早まったスピードとは一転して、安心感により極端にゆったりとしたペースになりがちです。
話すペースが不自然に速くなったり遅くなったりする場合は、早口部分が嘘の可能性が高いとみてよいでしょう。
特徴③嘘つきは具体的な話を避け、抽象的な話をする
とても単純な話で、嘘をついている人は具体的な細かい部分まで、事実ではなく想像で話す必要があります。
嘘を意識的についてみると分かるのですが、具体的な部分まで設定するのはとても骨が折れる作業なのですよね。具体的な話をすればするほど、後に矛盾してしまう可能性が高まってしまいます。
なので、嘘をついているときに人は具体的な話を避けようとして、なるべく抽象的な話に持っていこうとします。
具体的な質問をはぐらかし、話を逸したり抽象度を高めて回答してくる場合は嘘をついている可能性が高くなります。
特徴④嘘つきは髪をいじったり、クッションを抱きかかえたり身体的な行動が増える

人間は不安になると身体的な行動により不安を解消しようとします。
嘘をついている時は不安な感情があるため、髪をいじったり、クッションを抱きかかえたり、貧乏ゆすりが増えたりなど身体的な行動によって不安を解消しようとします。
どのような身体的な行動を取るかは人それぞれですが、一般的には元々している行動の頻度が高くなることがよくあります。
貧乏ゆすりを時々する人が貧乏揺すりをはじめたり、よく髪をいじっている人がいじり始めたりなどですね。
何かしらの身体的な行動が表れると嘘をついている可能性が高いです。
特徴⑤嘘つきは必要以上に見つめ続ける
個人的にこれは意外な特徴だったのですが、嘘つきは人の目を見つめ続けることが多いそうです。
嘘をついていない人は質問された際に、質問に集中するため視線を逸して回答しようと考えるのですね。
一方、嘘をついている人は質問に集中する必要がないため、視線を逸らさず見つめたままになりがちなのです。
嘘つきは不安な気持ちにより視線を逸らすと一般的に考えられがちですが、実際の研究では嘘つきほど見つめる傾向にあるようです。
“感覚的な嘘っぽい”を要素に分解してトレーニングしよう
日常生活を送っていると、嘘っぽいなと思うこともあると思います。
そんな時は上記5つの要素に当てはめて嘘つきを分解してみてください。
分解する意識をしていると、嘘の可能性が高いのか低いのかの判断ができるようになり、
嘘つきを見抜く精度も上がっていきます。
とはいえ、警察官や諜報員ではない我々にとって、嘘を見抜く能力ってそこまで必要がない能力なのですけどね笑